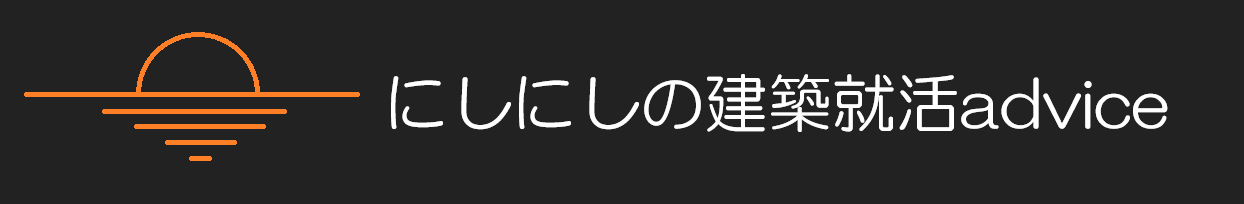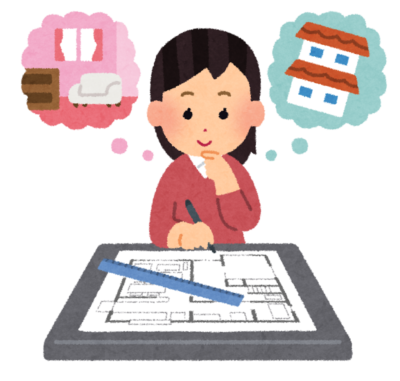アトリエ系・組織設計・ゼネコン・工務店の違いを徹底解説!
皆さんこんばんは!にしにしです。
今日は設計を目指す学生さんが気になっている数ある設計職の違いについて解説します。
はじめに
「設計」といっても、実は働く場所や会社の種類によって仕事内容や求められるスキルは大きく異なります。この記事では、建築学生が就職先として考えることの多い4つの設計職──「アトリエ系設計事務所」「組織設計事務所」「ゼネコン設計部」「工務店・ハウスメーカー」──について、それぞれの特徴や働き方、そして就活におけるポイントを紹介します。
将来のキャリアを考える上で、「どんな建築をつくりたいか」「どんな働き方が合っているか」を知ることはとても大切です。自分にフィットする進路選びのヒントになれば嬉しいです。
4つの設計職について個別解説
✅ アトリエ系設計事務所
【特徴】
比較的小規模で個人色の強い設計事務所。意匠デザインに強く、住宅や小規模建築を中心に、独自の世界観をもった設計を手がける。所長の名前が事務所名になっていることも多く、作品性・建築家性が重視される。
【働き方の特徴】
- 担当者が企画から設計・監理まで一貫して関わることが多い
- 少人数ゆえに業務は多岐にわたる(模型づくり、現場対応なども)
- 働き方は事務所ごとに差があり、長時間労働になりやすい傾向も
【就活のリアル】ポートフォリオが超重要/OB訪問がカギ
求人が公開されていないケースも多く、OB訪問や展示会での接点づくりが重要。ポートフォリオの完成度が判断基準として大きく、「この子と働きたい」と思わせる人柄と熱意の伝え方がカギ。狭き門だが、情熱と行動力がものをいう世界。
✅ 組織設計事務所
【特徴】
100人~数千人規模の社員を擁する大手設計事務所。オフィスビル、病院、大学、駅など大規模建築を得意とし、プロジェクトの規模も期間も大きい。
【働き方の特徴】
- 分業体制が整っており、各フェーズに専門部署がある
- ワークフローはしっかりしていて、残業や労働時間も管理されていることが多い
- チームワークと調整力が求められる
【就活のリアル】倍率は高いが、選考はオープン/技術的理解も評価
就活ルートは新卒採用がメイン。多くはインターンや会社説明会を経てエントリー。選考ではポートフォリオも見られるが、それだけでなく技術的な知識や論理的思考力が評価される傾向。倍率は高いが、きちんと準備すれば正攻法で勝負できるのが魅力。
✅ ゼネコン設計部
【特徴】
ゼネコン(総合建設会社)の中にある設計専門部署。設計と施工が同じ会社内で連携する「設計施工一貫」が特徴。意匠だけでなく構造・設備・施工の観点も強く関わる。
【働き方の特徴】
- 設計者としての立場と同時に、施工側との密な連携が求められる
- 実施設計・施工図の比重が大きい
- 社会インフラに近い建築を多く経験できる
【就活のリアル】設計志望は少数枠/説明会・面接で熱意を伝えるべし
ゼネコン全体の採用の中で「設計希望」は少数枠。そのため設計職での応募であることを強く伝えることが重要。構造や施工への興味も持ちつつ、「建築を形にする設計がやりたい」という姿勢が評価されやすい。インターン参加は選考に有利。
✅ 工務店・ハウスメーカーの設計職
【特徴】
戸建住宅を中心に、「顧客と直接やり取りしながら設計する」スタイルが多い。営業と連携して進めることも多く、接客的な要素も強い。
【働き方の特徴】
- プラン提案・打ち合わせ・申請・実施設計など全体に関わる
- 営業と一緒にお客様の夢をかたちにする“住宅の設計士”
- 土日勤務や営業同行がある会社も(企業により働き方は様々)
【就活のリアル】人物重視の傾向/プレゼン力が武器になる
採用は人物評価が高く、ポートフォリオよりも**「人柄・話し方・考え方」**が重視される傾向あり。設計職でも面接では「営業とも連携できますか?」「お客様に寄り添えますか?」という視点で見られる。プレゼン力・接客マインドが評価ポイント。
4つの設計職の初任給・お給料の目安
次に、それぞれの設計職について目安の初任給とお給料について下の表にまとめたのでご覧ください。
| 設計職の種類 | 初任給(目安) | 平均年収(30代前半~) | コメント |
|---|---|---|---|
| アトリエ系設計事務所 | 18〜22万円 | 300万〜450万円 | 給与は低め。独立や賞の受賞など“夢重視”の人向け。 |
| 組織設計事務所 | 22〜25万円 | 450万〜650万円 | 安定して昇給。福利厚生も手厚い傾向。 |
| ゼネコン設計部 | 23〜27万円 | 600万〜800万円 | 設計職の中では高水準。残業代・手当込みが多い。 |
| 工務店・ハウスメーカー | 21〜25万円 | 400万〜600万円 | 営業設計の場合は成果報酬あり。地域差あり。 |
ここでの年収とは総支給額を示しています。まだ社会人経験のない学生さんには感覚的になじみがないと思いますが、会社員であれば総支給額から『税金』と『社会保険料』が天引きされます。年収によって差はありますが、今の日本の制度ではおおよそ総支給から約30%が天引きされ、残りが手取りとなります。個人事業主ならこれに近い金額をご自身の手で納める必要があります。
どうでしょうか?上の表のお給料でご自身は生活していけそうでしょうか?
それぞれの職種の特徴から仕事を選ぶのも大切ですが、生きるためにはお金が必要です!
「元気があれば何でもできる!」とは言いますが「現金が無ければ何にもできぬ!」とも言いますw
夢と現実、どちらかに全振りするのでなく、両者をバランスよく選ぶことも大事です。
今後の社会変化があたえる設計職への影響
今社会が抱えている問題は徐々に深刻になりつつあります。少子高齢化と人口減少、働き方改革、AIの進化、などなど…。社会が目まぐるしく変化していく中で、建築の設計業界も少しずつ変化が求められているように感じています。
- スクラップ&ビルドから既存建物の活用
- BIMやAIを活用して作図業務や確認業務などの効率化
- テレワークによる設計スタイルの変化
こうした変化の中で、「人にしかできない設計力」や「クライアントの想いを汲み取る力」が今後より重要になると考えられます。
就活においても、単に知識やスキルだけでなく、**「自分の考えを持ち、相手に伝える力」や「多様な立場と協働できる力」**が求められるようになっていくでしょう。
まとめ
設計職といっても、その働き方や求められる力は本当に様々です。
- デザインの自由度を求めるなら → アトリエ系
- 大規模で社会性の高い建築に関わりたいなら → 組織設計・ゼネコン設計
- お客様の声を直接聞いて設計したいなら → ハウスメーカー・工務店
自分が「どんな建築を、誰のために、どのように設計したいか」を考えることで、進路はきっと見えてきます。ぜひこの記事を参考に、自分に合った設計の道を見つけてください!
それでは、まったね~♪