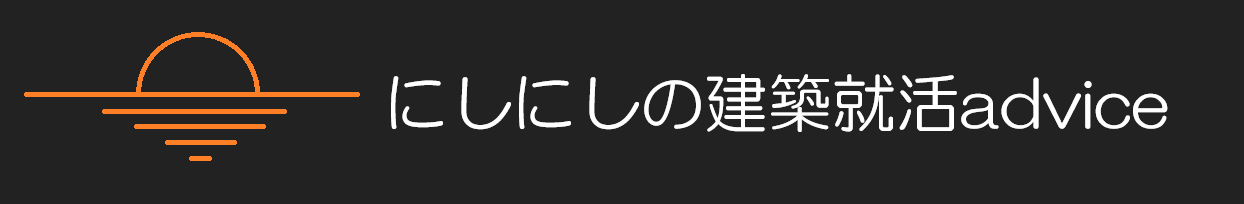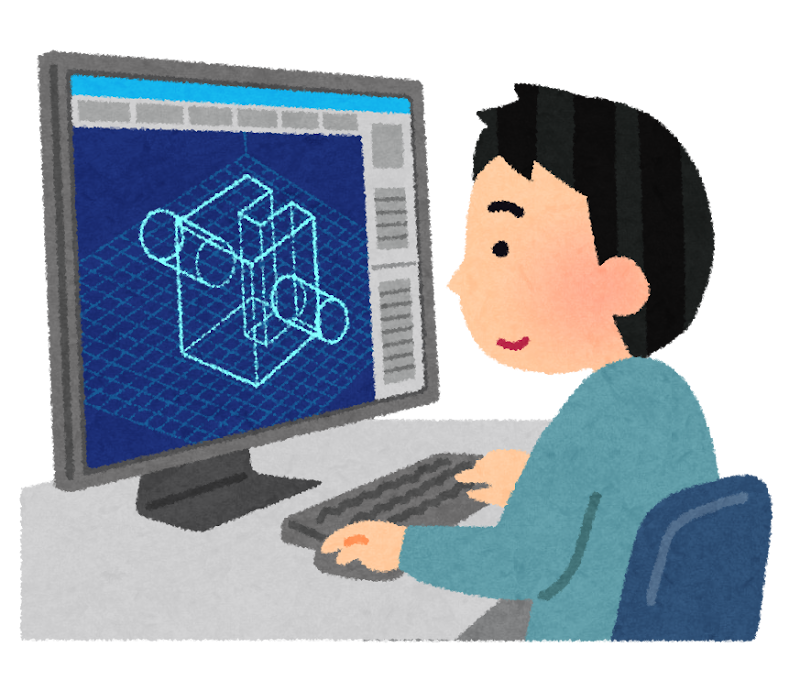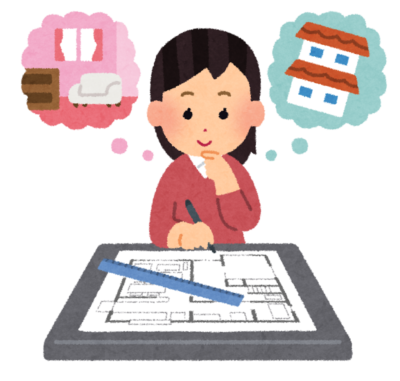こんばんは!にしにしです。
建築系の学生さんの多くは、学校の設計実習などで何かしらのCADを触ったことがあるかと思います。そして学校によって使用するCADソフトは様々だと思います。
『会社によって使用するCADは決まってるの?』
『いろんな種類のCADがあるけど、結局どれが使いやすいの?』
『これからはBIMが主流になると聞いたけど、実際どうなの?』
こんな疑問にお答えしつつ、今日は数あるCADソフトの中からメジャーなものをピックアップし解説していきます。
1. 建築業界で使用されているCADソフトの概要(代表例)
次の表に、メジャーなCADソフトについての特徴をまとめました。
| 分類 | ソフト名 | 製造元 | 主な特徴 | コスト | 建設業界での使用割合(参考) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2次元CAD | Jw_cad | 清水治郎氏と田中善文氏 | 無料・軽量で2D特化、日本の建築業界で広く普及 | 無料 | 中~高(中小ゼネコン・設計事務所・工務店) |
| AutoCAD | Autodesk(米) | 高機能な2D/3D汎用CAD、汎用性・信頼性が高い | 年間サブスク制(10万円前後) | 高(ゼネコン・設計事務所) | |
| ARCHITREND ZERO ※2DとBIMの良いとこどり |
福井コンピューター(日本) | 木造住宅向けBIM+CAD、確認申請・プレゼンに強い | 年間サブスク制(30万円前後) | 高(住宅会社・工務店) | |
| BIM | Revit | Autodesk(米) | BIM対応、3Dと情報管理の統合 | 年間サブスク制(30万円前後) | 中~高(大手ゼネコン・設計コンサル) |
| ArchiCAD | Graphisoft(ハンガリー) | 意匠設計向けBIMソフト、直感的な操作性が魅力 | 年間サブスク制(20万円前後) | 中(意匠事務所) | |
| Vectorworks | Vectorworks Inc.(米) | プレゼンにも強い、住宅設計向けとして人気 | 買い切り型(20万円前後) | 中(住宅系設計事務所) |
2. それぞれのソフトが使われている企業と選ばれている理由
次に、上に挙げたCADソフトについて、どんな企業が使用しているのか解説します。
- Jw_cad:中小規模の意匠・構造設計事務所や地域工務店で使用。シンプルで素早い操作が可能、修正作業が多い案件に向いている。フリーソフトであるため導入コストが不要。フリーソフトとしては非常に高い完成度を誇っている。これ以上の進化も無いが、これ以上の進化が必要ないCAD。
- AutoCAD:大手ゼネコンや総合設計事務所、官公庁案件での共通CADとして使用。業種問わず使用できる汎用性が魅力。建築以外の機械メーカー等もAutoCAD使用率が高いため互換性が非常に良い。カスタマイズ性も高く操作性に優れる。他との一番の違いは「モデル空間」と「ペーパー空間」という概念があり、この概念を生かせないとAutoCADの無駄遣いになる。
- ARCHITREND ZERO:ハウスメーカー、地域ビルダー、住宅系の設計事務所・工務店で広く採用。3D図面の作成、確認申請用の図面、構造検討、省エネ計算、法規チェックまで、木造住宅の設計に必要な要件が網羅されておりこれ1本で完結できる。導入・維持コストが高いので、年間棟数が確保できないと予算が厳しい。
- Revit:大手ゼネコン、大手設計事務所、設備設計会社などで採用。BIMによる干渉チェック・積算・情報共有の効率化が導入理由。製造元がAutodesk社なので、AutoCADとの連携が可能。すでにAutoCADを導入している企業がBIMを導入するなら間違いなくRevit<リベット>でしょう。
- ArchiCAD:デザイン重視の意匠系設計事務所やインテリア設計事務所で採用。3Dビジュアルとパース作成のしやすさが評価されている。毎年希望すればもらえるカレンダーがかっこいい。
- Vectorworks:戸建住宅・リフォーム・リノベーションを手がける設計事務所で人気。図面+プレゼンの両立が可能。BIMソフトの中では比較的低コストなため導入がし易い。
3. BIMとは?2次元CADや3D CADとの違いを解説
そもそもCAD<キャド>とBIM<ビム>の違いが分からない方もいらっしゃると思うので、簡単に解説いたします。
CAD(Computer Aided Design)とは
→ コンピュータ上で設計や製図を行うツール。
BIM(Building Information Modeling)とは
→ 単なる3Dモデルではなく、建物の情報(寸法・仕上・コスト・設備情報など)を一元管理する概念および手法です。
| 種類 | 特徴 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 2D CAD(例:Jw_cad) | 線と寸法で図面を描く | 意匠・構造図面の作図 |
| 3D CAD(例:SketchUp) | 形状の立体的な表現 | プレゼン・検討用モデル |
| BIM(例:Revit, ArchiCAD) | モデルに情報を付加、部材同士が連動 | 設計~施工~維持管理 |
2D CADは簡単に言えば、一昔前まで製図板を使って行っていた『製図』をPC上で行っているイメージ。
BIMは、単なる3D CADではなく、作図しながら部材ごとの材料・数量・耐久年数などの情報や、多種のパーツ同士の干渉をチェックしたり様々なメリットがあります。
しかしながら、機能が豊富ということは、裏を返すとそれだけ沢山の知識や操作テクニックが求められるということです。これを一人の設計者が実行するには作業量が多すぎて非現実的だと言えます。クラウド上にデータを保管し、複数の設計者で共有し同時作業ができる環境構築ができなければ導入の意義は無くなってしまうでしょう。また、一つの会社で完結させるのでなく、施工者、機械設備、電気設備、構造設計、鉄工所などと共有できることが最も理想的な形であるが、そのためには関係する企業全てが同じBIMソフトを整備しなければならず、現実的にはまだまだ夢物語な感が否めません。
4. 私が使っているJwCADについて ~まだまだ現役な理由~
私自身、日々の業務でJwCADを使っています。フリーソフトでありながら操作が非常に軽快で、2D作図においては今も第一線で活躍できるツールです。
私は以前の職場ではAutoCAD LTを使用していました。この時はAutoCAD最強!と思っていました。いえ、今もその考え変わっていません。
では、なぜ今Jw_CADを使用しているのか、その理由を説明いたします。
✅フリーソフトであること
私のように地方の建設会社で働いていると、自社だけでなく関連する協力業者の多くもJwCADを使っていることが多いです。そういった企業とデータのやり取りをする上で同じソフトであることは互換性の面でも非常に便利です。そして、この環境は向こう10年、いや20年以上は余裕で続くでしょう。
✅ショートカット・クロックメニューが素晴らしい
ずばり、JwCADが精密に作りこまれた操作性抜群のCADだからです。
AutoCADに慣れたあとにJwCADを使用すると、たいていの人がグレードダウンしたと感じてしまうかと思いますが、私はむしろフリーソフトなのにこれだけ無駄をそぎ落とし、必要な操作を凝縮し、繊細な設定ができるCADは最高傑作だと思っています。他のCADでもショートカットはありますが、JwCADはマニュアルに載っていない隠し操作がふんだんにあります。また、他のCADにはない”クロックメニュー”と言うマウス操作をパワーアップさせる操作もあります。おそらくこのソフトを開発された製作者様は、CADを使って製図をする動作を細かくイメージし、どんなプログラムを組めばより一瞬でも早く操作ができるかを追求されたのではないかと想像いたします。
✅BIMが普及するのはまだまだ先
社会的に業務効率化を求められている時代であり、そのような社会背景ではBIMは一気に普及するのでないかと思いたくなりますが、私はまだまだその時代が訪れるのは遠い未来だろうと思っています。
BIMの本質は“情報の網羅”であり、この本質を100%生かすには、意匠設計、構造設計、設備設計、建築施工者、設備施工者(電気・機械等)など複数の企業が足並みを揃えることが出来なければ意味が無いと思っています。フリーソフトならともかく、コストも高額であり、操作を覚えるのもかなりの時間と労力がかかるBIMソフトは、そう簡単に導入には至らないでしょう。
そして私の経験から言えることは、”デザインに全振りした設計者”がBIMを導入したところで、BIMの本質である“情報の網羅”ができるほど知識があるとは思えません。私は数ある現場を現場監督として経験してきましたが、施工に精通した意匠設計者は一握りしかいませんでした。施工を理解していない設計者が中途半端な情報を入力してしまうと、後に続く関係者に混乱が生じるのは明白でしょう。
以上よりJwCADは、他の高額なCADソフトよりも優れている面も多く、中小規模の建物の設計においてはまだまだ最前線で活躍できるCADだと言えます。
まとめ
CADやBIMといっても、実際にはソフトごとに特徴があり得意分野や導入のし易さが異なります。
企業によってはどのソフトを使用するかは各自の自由にしている会社もあるかもしれませんが、大半は企業が選択しているソフトを使用することになるでしょう。
- 意匠設計志望ならVectorworksやArchiCAD
- ゼネコン志望ならAutoCADやRevit
- 地元の設計事務所や工務店志望ならJw_cad
建築学生の皆様に覚えてほしいことは、どのCADソフトを使用することになっても、それぞれに得意分野や便利機能がありますので、そのCADが持つ能力をできる限り引き出してあげて欲しいということです。どんな道具も使い方次第ってことです。
それぞれの特徴を理解しながら、自分に必要なスキルを見極めていきましょう。
それでは、まったね~♪