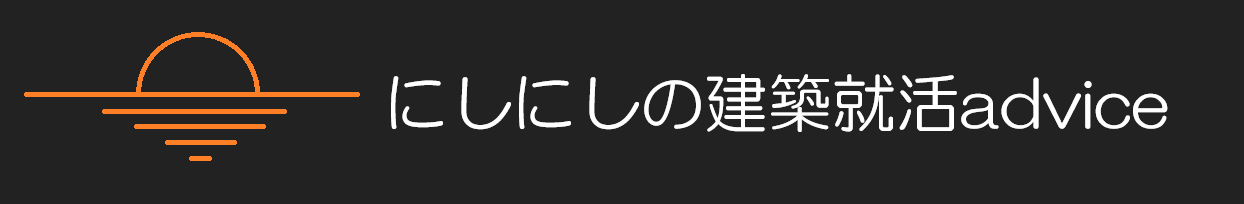みなさん、こんばんは。にしにしです。
現場監督を目指している、あるいは現在現場監督をされている若手の方の中にはこんな疑問を持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
現場監督に必要な資格と言えば、「建築施工管理技士」をまず最初に思い浮かべる人が多いかと思います。
今日は、「建築士」と「建築施工管理技士」の2つの資格の違いについてと、現場監督さんが「建築士」の資格を取得する理由について解説したいと思います。
施工図屋、現場監督、設計士と渡り歩いてきたハイブリッドな経歴を持つわたくし”にしにし”が建築業界のあれこれを分かり易くかみ砕いて解説していきます!
「建築士」「建築施工管理技士」が必要な業務とは?
皆さんは、この2つの資格の名前を聞くと
「建築士」=設計者に必要な資格
「建築施工管理技士」=現場監督に必要な資格
とお思いになるかと思います。
はい、ほぼ当たっています。
それではもう少し具体的に掘り下げていきましょう。
日本の建設業法においては、一定以上の請負金額以上の建築工事には「監理技術者」という資格者を設置する必要があると定められています。
この「監理技術者」になるためには「一級建築施工管理技士」又は「一級建築士」のどちらかの資格があればなれます。
ちなみによく似たものに、「主任技術者」というものがあります。
この「主任技術者」になるためには、先に挙げた2つの“一級”資格に加えて「二級建築施工管理技士」と「二級建築士」の資格者でもなることが可能です。これについては詳しく話すと長くなりますので別の機会にまとめたいと思います。
そうなんです。別に施工管理技士だけが監理技術者になれるわけではないのです。
つまり一級建築士の資格を持っているだけでも監理技術者にはなれるのです。
ちなみに私の会社にも実際に「一級建築施工管理技士」を持たず「一級建築士」のみ取得している現場監督さんも居ます。
では逆に、設計業務(または監理業務)を行うには「建築士」でないとできないのでしょうか?
その答えは、、、YES! こればっかりは建築士でないとできないのです。
設計・監理については建築士法で定められています。これについても別の機会に詳しく解説したいと思います。
「建築士」だけあれば現場監督は成り立つのか?
こう聞くと「一級建築士」を持っていれば、どんな建築現場でも監理技術者になれそうな気がしますね。わざわざ「一級施工管理技士」を取る必要ないじゃないか?と思われるでしょう。
あながち間違ってはいませんが、これには少し注意点があります。
建設業には、様々な業種があります。
「大工」「左官」「屋根」「建具」などなど、個別の業種が沢山あり、それらの業種を複数に渡って総合的に請け負う工事を「建築一式工事」と呼びます。
「一級建築施工管理技士」と「一級建築士」とでは、それら個別の業種の内、監理技術者になれる工種に若干の違いがあるのです。
とは言え現実的には、単独の業種のみで監理技術者設置の要件に該当する請負4000万円以上になることはめったになく、たいていはそれに付随する他の業種とセットになることが多いので「建築一式工事」となる場合が多いでしょう。(6000万円以上で監理技術者設置要)
「建築一式工事」については「一級施工管理技士」も「一級建築士」でもどちらでも監理技術者になれます。
しかし、建築会社に勤めていると意外とちょくちょくあるのが「解体工事」です。
既存の建物を建て替えしようとするとき、まず解体から入りますよね。
建築工事と解体工事を分けて発注されることってよくあるんです。
ここで冒頭の注意点になります。
「一級建築士」には「解体工事」の監理技術者にはなれないのです。
この点については、地味ではありますが注意が必要かなと思っています。知らずにやってしまうと違反になっちゃいますからね。
まぁ会社的には重要かもしれませんが従業員の立場からすると、資格持ってる人が行けばいいので、そんなに大きな問題んではないですねw
「建築施工管理技士」と「建築士」試験の難易度は?
どちらの資格にも”一級”、”二級”とランクがあり、はたから見ると同級の資格同士なら同格の資格なのかなとお思いになるかと思います。
そんなことを一級建築士様の目の前で言ったら発狂して暴れだします!
嘘です。それは大げさに言いすぎですが、心の奥底では「一緒になんかしてくれるな」と思っているはずです。
そもそも業務内容が違うので本来比べるべきではないのですが、なにせ難易度が全然違います!
ネットで「資格 難易度ランキング」と検索するとすぐにランキングが出てきます。
参考サイト:資格難易度ランキング 1位~700位 – 資格の取り方
このランキングサイトによると、「一級建築士」の難易度は66。
「一級施工管理技士」は55なので、一回り以上の差が開いています。
ちなみに「二級建築士」はというと、56ありますので若干「二級建築士」の方が難しいと言えます。それだけ建築士の方が試験範囲が広く難しいのです。
余談ですが、一般の人にもイメージし易いように比較対象を挙げますね。
「日商簿記検定一級」・・・67
「航空管制官」「社労士」・・・65
「土地家屋調査士」「気象予報士」・・・64
「歯科医師」「国家公務員(一般職)」・・・63
「薬剤師」「管理栄養士」「プロゴルファー」・・・62
「日商簿記検定二級」・・・58
「宅建」・・・57
といった感じです。
ちなみに私の経験談ですが、二級建築士は真面目に勉強すれば市販の過去問だけで独学で取れます。とれない人は真面目じゃない人ですw
一級建築施工管理技士も、一級建築士の試験のついでに受けたらあっさり取れてしまいます。
一級建築士を取ろうと思っている皆さんにお伝えします。
素直に資格学校に行って勉強することをお勧めします。
そして、資格学校にただ通っているだけでは受かりません。やることちゃんとやらないと無理ですよ。
一級建築士に独学で合格できる人は、僕ら凡人とは頭の作りが違うのでしょう。
現場監督に「建築士」は必要か?
結論から申し上げます。
現場監督にとって「建築士」は「見栄」でしかありませんw
本業の監理技術者になるだけなら「一級建築士」よりはるかに簡単な「一級建築施工管理技士」だけを取る方が楽で効率がいいわけで、わざわざ膨大な時間と労力と命を削ってまで「一級建築士」を所得する必要はないのです!(言っちゃったwww)
それでも、世の現場監督の中には「一級施工管理技士」と「一級建築士」のダブル国家資格を自身の名刺に刻む“ツワモノ”もおります。そんなツワモノに出会った際には、一言でいいので「両方持ってるなんて凄いですね!」と添えるだけで心の中でニヤッとしているはずですwww
現場監督が「建築士」を取るメリット
現場監督さんにとって不必要と言った「建築士」ですが、私個人的な意見としては「一級建築士」または「二級建築士」どちらかだけでもいいので取得に励んでみてほしいと思っています。
物理的なメリットとして、会社から資格手当が支給されるからです。(資格手当がない会社の方はこのメリットは享受できません)
頂ける金額は会社によって様々ですが、仮に給料が月1万円上がったとしたら、1年で12万円、10年で120万円もらえます。もっと沢山支給される会社であればもっと大きな差が生まれるでしょう。サラリーマンとしてはこの差が絶大です!早く取った方が賢明なのは一目瞭然ですよね。
そして精神的なメリットとして、「建築士」を持っていることで、周りからの信頼度も上がりますし、何より勉強に費やした膨大な努力が支えとなり、何かに取り組む際の心の支えになってくれます。
自分はやればできるんだ!
あの時の困難に比べたらこんなもんへっちゃらだ!
なんて思えちゃうんです。
是非、多くの若手の皆さんにチャレンジしてほしいと思います。
まとめ
Q.「建築士」「建築施工管理技士」が必要な業務とは?
A.「監理技術者」の専任が必要な工事に必要。
Q.「建築士」だけあれば現場監督は成り立つ?
A.「建築一式工事」はどちらの資格でも可能。ただし「解体工事」については「一級建築士」のみでは監理技術者にはなれません。
Q.「建築施工管理技士」と「建築士」試験の難易度は?
A.「一級建築士」がダントツで難しい。難易度66
「一級建築施工管理技士」55と「二級建築士」56がほぼ同じ難易度。
「二級建築施工管理技士」は、ご自身でお調べください。
Q.現場監督に「建築士」は必要か?
A.業務的には不要です。ただし次にあげるメリットはあります。
Q.現場監督が「建築士」を取るメリット
A.物理的なメリットとして、給料が上がる。
精神的なメリットとして、周りからの信頼度があがる。自分に自信がつく。
以上、現場監督に「建築士」の資格は必要か?というテーマでお話ししました。
だいぶ主観が入った解説となりましたが、時には理論的に、時には精神論でこれからも解説していきたいと思います。
それでは、まったね~