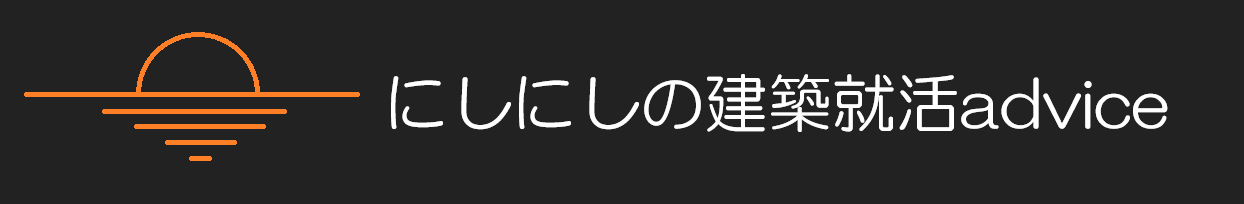皆さんこんばんは!にしにしです!
建築の学生さんの中で建築士の資格取得を考えている方は少なくないと思います。
しかし多くの学生さんは、そもそも資格試験自体が初めてだったりして、どうやって受験するのかさっぱり分からんって方もいるのではないでしょうか?
今日は、建築士の試験について解説していきます。
① 建築士の種類をざっくり解説
建築士には大きく「一級建築士」「二級建築士」「木造建築士」の3種類があります。
さらに「一級建築士」には派生形として「構造設計一級建築士」「設備設計一級建築士」の2種類があります。
ざっくりと説明すると、、、
「一級建築士」・・・非住宅建築物の意匠設計者向け
「二級建築士」・・・戸建て住宅や小規模建築物の意匠設計者向け
「木造建築士」・・・大工さんなど
「構造設計一級建築士」・・・その名の通り、構造設計者向け
「設備設計一級建築士」・・・その名の通り、設備設計者向け
② 「一級建築士」「二級建築士」になるためには?
今回は代表的な「一級建築士」「二級建築士」に絞って解説します。
建築士になるためには「受験資格」と「登録要件」という2つの条件を満たす必要があります。
1つ目の受験資格というのは、その条件を満たしていないと受験できませんよ。という意味です。
2つ目の登録要件というのは、合格してもこの条件に満たすまでは免許はお預けですよ。という意味です。
👉ここがポイント!
試験に合格したら免許もらえるんじゃないの?って普通は思いますよね。実は少し前まではちゃんとそういう制度になっていました。
じゃあ、なんでこんなややこしいことになっているのかというと、その背景として少子高齢化などの社会情勢により建築士の総数が減少してきたためです。
何とかして建築士の数を増やしたかった政府が、若い世代に少しでも多く建築士試験を受験してもらうために、令和2年に法改正を行い、実務経験に満たなくても受験ができるようにしてくれました。
③ 受験資格について解説
まず受験資格について下の表にまとめました。

ざっくり解説すると、
- 一級、二級ともに所定の学歴を満たしていれば、卒業後すぐに“受験”可能!
- 建築系の工業高校を卒業すれば、最短で二級建築士を”受験”可能!
- 二級は、建築系の学歴が無くても受験は可能だが、実務経験が7年必要。
- 建築系の学歴が無い人が一級建築士になるには、「二級建築士」または「建築設備士」を取る以外にない。
④ 登録要件について解説
次に登録要件について下の表にまとめました。

ざっくり解説すると、
- 一級は卒業校の種類によって、必要な実務経験年数が違うので注意。
- 二級で高等学校・中等教育学校卒の人は2年の”実務“経験が必要。進学した場合は進学した年数分お預けとなる点に注意。
⑤ にしにしのおすすめルート
このように建築士資格を取得するには、受験資格と登録要件の2つの要素が関係してきます。 この制度をうまく利用することがより早く建築のキャリアを積む近道となります!
そこで、にしにしがおススメする最適ルートをご紹介します!
(1)一級・二級同時受験で一石二鳥ルート
所定の学校卒業後、実務経験なしで受験できることを利用して2つ同時に受験してしまう方法です。
当然ながら一級建築士は二級建築士の上位互換です。一級建築士の資格学校に通うことで、資格学校の学費を1回で済ます方法です。
この方法だと仮に一級が落ちても保険として二級が滑り止めになるため安心感が高まります。
(2)在学中に二級取得で就職有利ルート
一部の専門学校などでは在学中に二級建築士を受験可能な学校がいくつかあります。
私も実はこのルートで在学中に二級を取った口です。
このルートのメリットは、断然就職に有利という点です。だって二級持って就活ですよ!無いのと有るのでは差は大きいでしょう!当然就職直後から資格手当もありますしね💴
ちなみに在学中に勉強できるので、特別に資格学校には通っていません。市販の過去問のみで1発合格しました。結果、コスパ最強でしたw
計画通りに運ばなかったのはその後の一級で、舐めてかかったために3回落ちたということです😱
まとめ
- 建築士の種類について解説
- 建築士には「一級建築士」「二級建築士」「木造建築士」の3種類があり、さらに「一級建築士」には派生形として「構造設計一級建築士」「設備設計一級建築士」がある。
- 建築士になるためには次の2つの要件を満たす必要がある。
- 受験資格を満たし試験に合格する。
- 合格後、登録要件を満たし免許登録を申請する。
- 受験資格について解説。
- 登録要件について解説。
- にしにしのおすすめルート
- 一級、二級を同時受験で一石二鳥ルート
- 在学中に二級取得で就職有利ルート
以上、ここまで建築士を取得するまでの流れをざっくり解説してきました。
時代とともに試験の要件も変わってきています。この先の未来ではどのようになっているかは分かりません。今よりさらに試験の難易度が上がっているかもしれませんし、建築士を量産するために”三級建築士”なんてものが生まれてくるかもしれませんw
しかし、私から皆さまにお伝えすることはただ一つです。
時代の流れや周りの風潮に惑わされず、今自分ができる最善策を取ることに集中しましょう!
私にしにしは、いつどんな時も皆様の明るい将来を応援しております。
昨日より今日、今日より明日を大切にがんばりましょう!
それじゃ、またね~♪